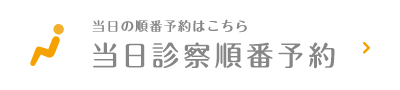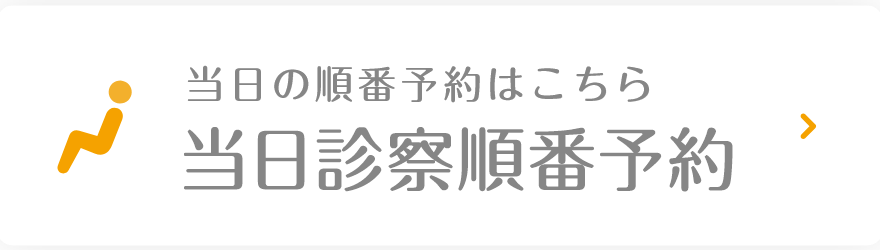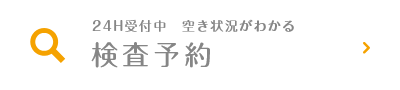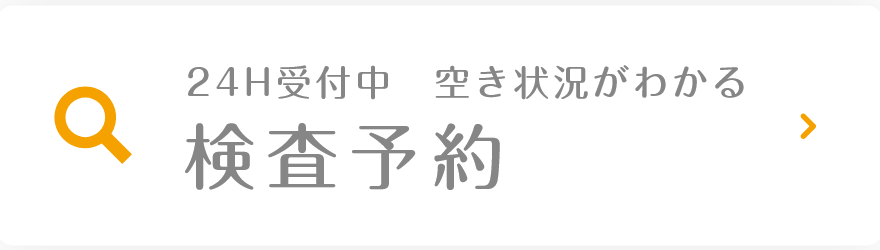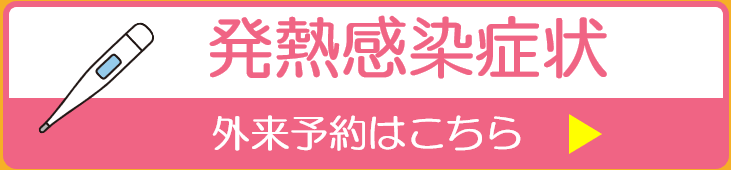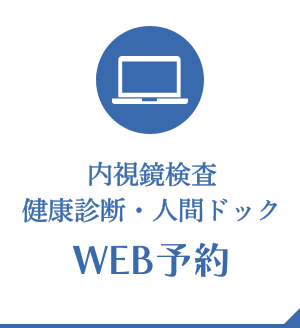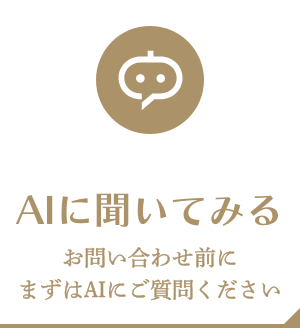脂質異常症(高脂血症・高コレステロール血症)
脂質異常症(高脂血症・高コレステロール血症)
1. 定義と分類
脂質異常症は、血液中の脂質(コレステロール、トリグリセライドなど)が異常値を示す病態です。動脈硬化の主要な危険因子であり、心血管疾患のリスクを高めます。以前は高脂血症と呼ばれていました。
分類
日本動脈硬化学会による「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」では、以下の分類が用いられています<sup>1</sup>。
- LDLコレステロール(LDL-C)高値血症:
- 高LDL-C血症:140 mg/dL以上
- 境界域高LDL-C血症:120~139 mg/dL
- Non-HDLコレステロール(non-HDL-C)高値血症:
- 高non-HDL-C血症:170 mg/dL以上
- 境界域高non-HDL-C血症:150~169 mg/dL
- トリグリセライド(TG)高値血症:
- 高TG血症:150 mg/dL以上
- HDLコレステロール(HDL-C)低値血症:
- 低HDL-C血症:40 mg/dL未満
これらの病型は単独で存在することもあれば、複合的に出現することもあります。
2. 病因と危険因子
脂質異常症の病因は多岐にわたり、遺伝的要因と環境要因が複雑に関与します。
遺伝的要因:
- 家族性高コレステロール血症
- 家族性複合型高脂血症
- リポ蛋白リパーゼ欠損症
- アポ蛋白異常症
環境要因:
- 食生活: 飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロールの過剰摂取、高カロリー食
- 運動不足
- 肥満
- 喫煙
- 過度の飲酒
- 加齢
- 基礎疾患: 糖尿病、甲状腺機能低下症、腎疾患、閉塞性黄疸など
- 薬剤: 利尿薬、β遮断薬、経口避妊薬、ステロイドなど
3. 臨床症状と診断
脂質異常症自体には自覚症状がほとんどありません。しかし、長期間放置すると動脈硬化が進行し、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの重篤な心血管疾患を引き起こす可能性があります。
診断:
- 血液検査: 空腹時の血清脂質(総コレステロール、LDL-C、HDL-C、TG)を測定します。non-HDL-Cも評価に有用です。
- 詳細な問診: 家族歴、既往歴、生活習慣、内服薬などを確認します。
- 二次性脂質異常症の鑑別: 基礎疾患の有無を確認するための追加検査が必要となる場合があります(甲状腺機能検査、腎機能検査、肝機能検査など)。
4. 治療
脂質異常症の治療目標は、心血管疾患の発症・進展抑制です。治療は、生活習慣の改善を基本とし、必要に応じて薬物療法を併用します。
4.1 生活習慣の改善:
- 食事療法:
- 飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロールの摂取制限
- 食物繊維の摂取増加
- 多価不飽和脂肪酸(n-3系脂肪酸など)の摂取
- 適正なエネルギー摂取
- 運動療法:
- 有酸素運動を中心とした регулярная физическая активность (例:ウォーキング、ジョギング、水泳など)
- 1回30分以上、週3回以上を目安
- 禁煙
- 節酒
- 体重管理
4.2 薬物療法:
生活習慣の改善だけでは目標値を達成できない場合や、心血管疾患のリスクが高い場合には薬物療法を検討します。
- HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン): LDL-C低下作用が強く、第一選択薬となることが多いです。
- 小腸コレステロール吸収阻害薬(エゼチミブ): 主にLDL-Cを低下させ、スタチンとの併用も可能です。
- プロブコール: LDL-C、HDL-Cを低下させる作用があります。
- 陰イオン交換樹脂: LDL-Cを低下させますが、TGを上昇させる可能性があります。
- フィブラート系薬: 主にTGを低下させ、HDL-Cを上昇させる作用があります。
- ニコチン酸誘導体: LDL-C、TGを低下させ、HDL-Cを上昇させる作用がありますが、副作用に注意が必要です。
- PCSK9阻害薬: LDL-Cを強力に低下させ、家族性高コレステロール血症やスタチン抵抗性の高LDL-C血症に用いられます。
- CETP阻害薬: HDL-Cを上昇させる薬剤ですが、臨床試験の結果を踏まえ慎重な使用が求められます。
- n-3系多価不飽和脂肪酸製剤: 主にTGを低下させる作用があります。
薬物療法の選択は、患者の脂質プロファイル、心血管リスク、合併症などを考慮して個別に行われます。
5. 治療目標
治療目標値は、患者の心血管リスクに応じて設定されます。「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」では、リスク層別にLDL-C、non-HDL-Cの目標値が示されています。
- 低リスク: LDL-C ; 120 mg/dL, non-HDL-C ; 150 mg/dL
- 中リスク: LDL-C ; 100 mg/dL, non-HDL-C ; 130 mg/dL
- 高リスク: LDL-C ; 70 mg/dL, non-HDL-C ; 100 mg/dL
- 極めて高リスク: LDL-C ; 50 mg/dL, non-HDL-C ; 80 mg/dL
糖尿病患者、慢性腎臓病患者、家族性高コレステロール血症患者など、個別のリスク評価に基づいたより厳格な目標値設定が必要となる場合があります。
6. 予後と管理
脂質異常症は慢性疾患であり、多くの場合、生涯にわたる管理が必要です。定期的な脂質検査を行い、治療効果や副作用を評価しながら、生活習慣の改善を継続し、適切な薬物療法を行うことが重要です。患者教育も、治療継続のためには不可欠です。
出典
- 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版. https://www.google.com/search?q=https://www.j-athero.org/guideline/pdf/JAS_GL2022.pdf