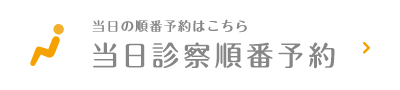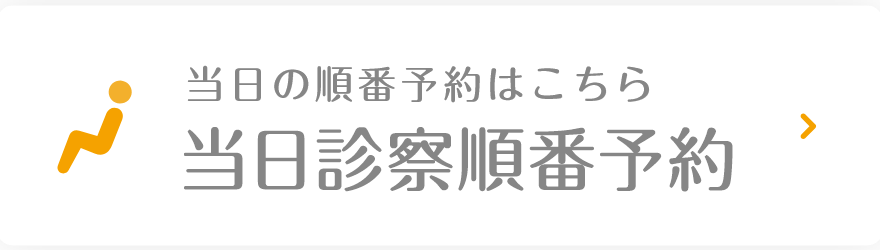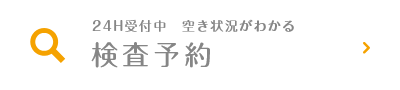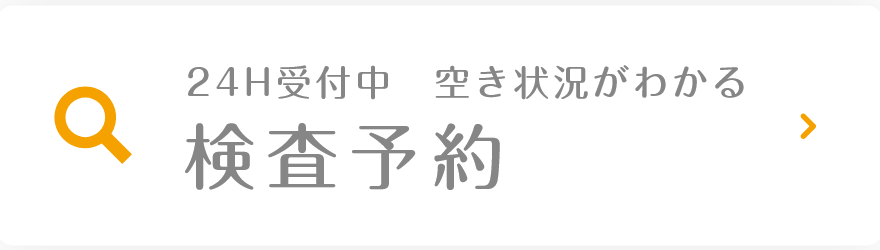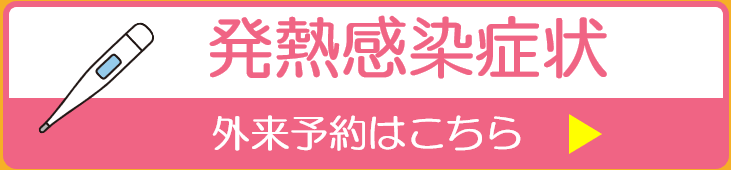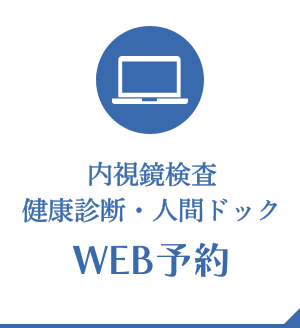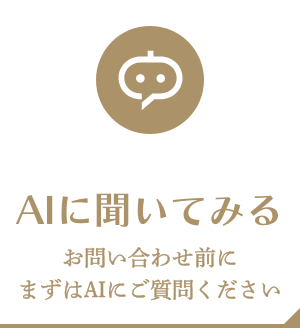肝炎ウイルス感染症
肝炎ウイルス感染症
1. 肝炎ウイルスの種類と特徴
現在、主要な肝炎ウイルスとしてA型、B型、C型、D型(デルタ)、E型肝炎ウイルスが知られています。それぞれ異なる特徴、感染経路、臨床経過、治療法を有します。
2. 各肝炎ウイルスの臨床像と診断
2.1. A型肝炎 (Hepatitis A Virus: HAV)
- 臨床像: 急性肝炎として発症し、発熱、倦怠感、食欲不振、黄疸などを呈します。通常、慢性化することはありません。
- 診断: 抗HAV IgM抗体の検出が急性感染の診断に有用です。既往感染やワクチン接種の確認には抗HAV IgG抗体を測定します。
- 最新の知見: 国内外で散発的な流行や集団感染が報告されています。性的接触による感染も注目されています。[1]
2.2. B型肝炎 (Hepatitis B Virus: HBV)
- 臨床像: 急性肝炎として発症する場合と、無症候性キャリアとなる場合があります。慢性肝炎、肝硬変、肝細胞癌への進行リスクがあります。
- 診断: HBs抗原、HBe抗原/抗体、HBc抗体、HBV DNA量などを測定し、感染状況やウイルス量を評価します。
- 最新の知見: 核酸アナログ製剤やインターフェロン製剤による治療が進歩し、ウイルス量の抑制や肝線維化の改善が期待できます。近年、Pegylated interferon lambdaも臨床試験で有望な結果が示されています。[2] また、機能的治癒を目指した新規治療薬の開発も活発です。[3]
2.3. C型肝炎 (Hepatitis C Virus: HCV)
- 臨床像: 急性肝炎は無症状であることが多く、慢性化しやすいのが特徴です。慢性肝炎から肝硬変、肝細胞癌へと進行するリスクがあります。
- 診断: 抗HCV抗体の検出がスクリーニングに用いられ、HCV RNA量の測定でウイルス量を評価します。ジェノタイプ判定は治療薬選択に重要です。
- 最新の知見: 直接作用型抗ウイルス薬(Direct-Acting Antivirals: DAAs)の登場により、高いウイルス排除率と良好な忍容性が得られるようになりました。パンジェノタイプDAAsの普及により、ジェノタイプ判定が不要となるケースも増えています。[4]
2.4. D型肝炎 (Hepatitis D Virus: HDV)
- 臨床像: B型肝炎ウイルスとの重複感染(同時感染または重感染)でのみ成立します。B型肝炎の症状を増悪させ、慢性化や肝硬変への進行を加速させる可能性があります。
- 診断: 抗HDV抗体やHDV RNAを測定します。
- 最新の知見: Pegylated interferon alphaが主な治療法ですが、効果は限定的です。近年、HDVの侵入や複製を阻害する新規薬剤の開発が進められています。[5]
2.5. E型肝炎 (Hepatitis E Virus: HEV)
- 臨床像: 主に急性肝炎として発症し、黄疸を伴うことが多いです。通常、慢性化しませんが、免疫不全患者では慢性化する例が報告されています(主に3型、4型)。
- 診断: 抗HEV IgM抗体の検出が急性感染の診断に有用です。抗HEV IgG抗体は既往感染の指標となります。HEV RNAを測定することもあります。
- 最新の知見: 輸血や臓器移植による感染例、加熱不十分な豚肉やイノシシ肉の摂取による感染例が報告されています。国内では genotype 3 および 4 が主に検出されます。[6]
3. 治療と管理
各肝炎ウイルス感染症に対する治療と管理は、ウイルスの種類、感染状況(急性/慢性)、肝機能、合併症などを考慮して個別に行われます。
- A型肝炎、E型肝炎: 基本的に対症療法が中心となります。
- B型肝炎: 核酸アナログ製剤やインターフェロン製剤による抗ウイルス療法が行われます。定期的な肝機能検査や画像検査による経過観察が重要です。
- C型肝炎: DAA製剤による抗ウイルス療法が第一選択となります。治療後の経過観察も重要です。
- D型肝炎: Pegylated interferon alphaによる治療が主に行われます。B型肝炎に対する治療も併せて行う必要があります。
4. 予防
- A型肝炎: ワクチン接種が有効です。
- B型肝炎: ワクチン接種が有効です。母子感染予防対策も重要です。
- C型肝炎: 有効なワクチンはありません。血液感染予防が重要です。
- D型肝炎: B型肝炎ワクチン接種により予防可能です。
- E型肝炎: 加熱不十分な肉の摂取を避ける、衛生的な生活習慣が重要です。一部地域ではワクチンが利用可能です。
5. 最新の知見と今後の展望
肝炎ウイルス研究は日々進歩しており、新たな診断法や治療法の開発が期待されています。特にB型肝炎の機能的治癒に向けた研究、D型肝炎に対する新規治療薬の開発、そしてC型肝炎後の長期的な管理などが重要な課題となっています。また、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)との関連性や、肝炎ウイルス感染者の高齢化に伴う合併症管理も重要性を増しています。
引用文献
- Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis A. https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/index.htm
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2017;67(2):370-398.
- Lok AS, McMahon BJ, Brown RS Jr, et al. AASLD practice guidance for the treatment of chronic hepatitis B: a 2018 update. Hepatology. 2018;67(4):1560-1599.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol. 2018;69(2):461-511.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis D virus infection. J Hepatol. 2016;64(6):1319-1335.
- World Health Organization. Hepatitis E. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e
東戸塚メディカルクリニック