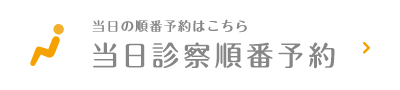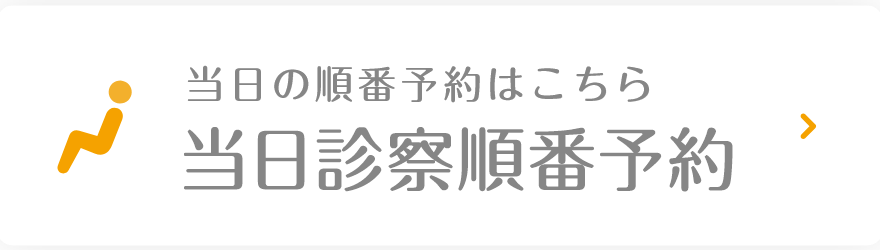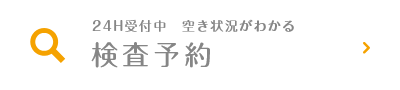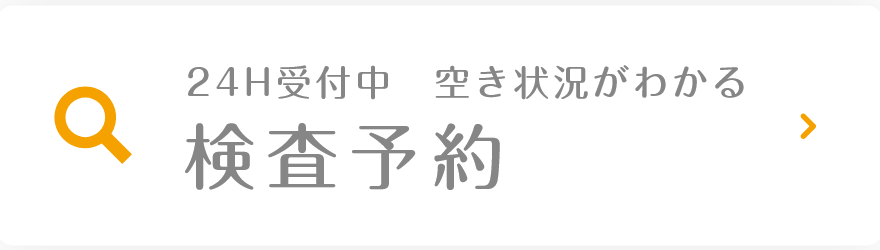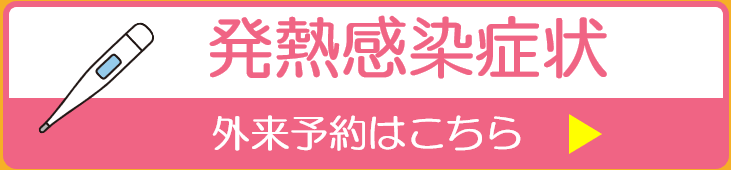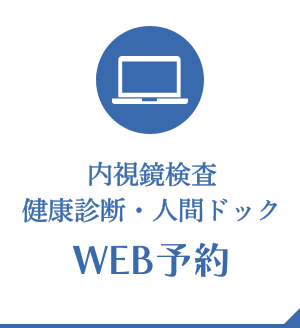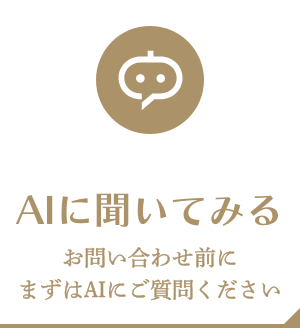アニサキス症
アニサキス症
1. 定義と原因
アニサキス症は、アニサキス属の幼虫が寄生した魚介類を生または加熱不十分な状態で摂取することにより、消化管壁に幼虫が侵入して引き起こされる疾患です。激しい腹痛、嘔吐、蕁麻疹などの症状を呈します。[1]
原因となるアニサキス属の幼虫には、主に Anisakis simplex (アニサキス・シンプレックス) と Anisakis pegreffii (アニサキス・ペグレフィイ) が知られています。[2] これらの幼虫は、サバ、アジ、イワシ、サケ、マス、イカなどの魚介類の内臓に寄生し、死後筋肉に移行することがあります。
2. 疫学
日本は生魚を食べる習慣があるため、アニサキス症の発生件数が比較的多い国です。年間数千件の報告があるとされていますが、実際にはさらに多くの患者が存在すると考えられています。[3] 近年、食の多様化や流通の変化に伴い、アニサキス症の発生傾向にも変化が見られています。
3. 病態生理
アニサキス幼虫がヒトの消化管壁に侵入すると、異物反応として炎症が引き起こされます。幼虫はヒトの体内では成虫になれないため、通常は数日~数週間で自然に死滅しますが、その間、強い症状を引き起こすことがあります。[1]
アレルギー反応もアニサキス症の重要な病態の一つです。アニサキスの体成分に対するIgE抗体が産生されると、再摂取時に蕁麻疹、血管性浮腫、アナフィラキシーなどのアレルギー症状を呈することがあります。[4]
4. 臨床症状
アニサキス症の主な症状は、摂取後数時間~十数時間以内に起こる急性胃アニサキス症による激しい腹痛(心窩部痛が多い)、嘔吐です。[1]
その他の消化器症状として、悪心、下痢などがみられることもあります。
まれに、腸管アニサキス症を発症し、腹痛、腹部膨満感、腸閉塞などの症状を呈することがあります。症状出現までに数日~数週間かかることもあります。[5]
アニサキスアレルギーの場合、魚介類摂取後すぐに蕁麻疹、血管性浮腫、呼吸困難などのアレルギー症状が出現します。過去にアニサキス症の既往がない場合でも、アニサキスに対する感作が成立していればアレルギー反応を起こすことがあります。[4]
5. 診断
アニサキス症の診断は、主に以下の情報に基づいて行われます。[1]
- 病歴: 生または加熱不十分な魚介類の摂取歴、症状出現までの時間、症状の内容などを詳しく聴取します。
- 内視鏡検査: 急性胃アニサキス症の場合、胃内視鏡検査で胃壁に穿入したアニサキス幼虫を直接確認できることがあります。鉗子で摘出することで、診断と治療を兼ねることができます。
- 画像検査: 腸管アニサキス症の場合、腹部X線検査やCT検査で腸管壁の肥厚や狭窄、腸閉塞などの所見がみられることがあります。
- 血液検査: アニサキスアレルギーが疑われる場合には、血清中のアニサキス特異的IgE抗体を測定します。好酸球増多がみられることもあります。
- 病理組織検査: 手術などで摘出された消化管壁や虫体を病理学的に検査することで、確定診断が得られます。
6. 治療
アニサキス症の治療は、主に以下の方法が行われます。[1]
- 対症療法: 軽症の場合や、内視鏡検査で幼虫が確認できない場合は、鎮痛薬や制吐薬などを用いて症状を緩和します。
- 内視鏡的摘除: 急性胃アニサキス症で、内視鏡検査により胃壁に穿入した幼虫が確認できた場合は、鉗子を用いて摘出します。これにより、速やかに症状が改善することが期待できます。
- 外科的治療: 腸管アニサキス症で、腸閉塞や穿孔などの合併症を起こしている場合は、手術が必要となることがあります。
- アニサキスアレルギーの治療: アレルギー症状に対しては、抗ヒスタミン薬、ステロイド薬、アドレナリン自己注射薬などが用いられます。重症度に応じて適切な治療を行います。
7. 予防
アニサキス症の予防には、以下の対策が重要です。[6]
- 加熱調理: 魚介類の中心部を60℃で1分以上加熱することで、アニサキス幼虫は死滅します。
- 冷凍処理: -20℃以下で24時間以上冷凍することで、アニサキス幼虫は死滅します。家庭用冷凍庫では、より長い時間の冷凍が必要です。
- 目視による確認と除去: 生食用の魚介類は、調理前に内臓を速やかに除去し、筋肉を目視で確認してアニサキス幼虫がいないか確認します。幼虫を発見した場合は、取り除く必要があります。
- 鮮度の維持: 魚介類の鮮度を保つことで、アニサキス幼虫が筋肉に移行するのを遅らせることができます。
8. 最新の知見
近年、アニサキス症に関する研究も進んでおり、新たな知見が得られています。
- アニサキスの種同定: 分子生物学的手法を用いたアニサキスの種同定が進み、地域や魚種による寄生種の違いなどが明らかになってきています。[2]
- アニサキスアレルギーの研究: アレルゲンタンパク質の特定や、アレルギー発症メカニズムの解明が進んでいます。経口免疫療法などの新たな治療法の研究も行われています。[7]
- 画像診断の進歩: 腸管アニサキス症におけるCTやMRIなどの画像診断の有用性が報告されています。
- 予防法の啓発: 消費者に対する正しい知識の普及や、食品事業者における衛生管理の徹底が重要視されています。
- 簡便な検査キットの開発: アニサキス抗体を簡便に検出できる検査キットの開発が進められています。
9. 出典
- 厚生労働省. アニサキス症とは. (参照 2025-04-26). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042953.html
- Ube M, Ishida Y, Sugiyama H, et al. Molecular identification of Anisakis species from marine fish in Japan. Parasitol Res. 2014;113(1):197-202.
- 国立感染症研究所. アニサキス症とは. (参照 2025-04-26). https://www.google.com/search?q=https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/401-anisakis.html
- Audicana MT, Kennedy MW. Anisakis simplex: from obscure worm to paradigm of food-borne parasitic allergy. Clin Microbiol Rev. 2008;21(1):15-31.
- Fujita R, Ohta N, Yoshikawa M. Intestinal anisakiasis: clinical manifestations, diagnosis, and management. World J Gastroenterol. 2016;22(41):9151-9157.
- 消費者庁. アニサキスによる食中毒を予防するために. (参照 2025-04-26). https://www.google.com/search?q=https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_safety/microbial/cause/anisakis/
- Kimura Y, Ando T, Seishima M. Anisakis allergy: clinical aspects, diagnosis, and management. Allergol Int. 2020;69(2):177-183.