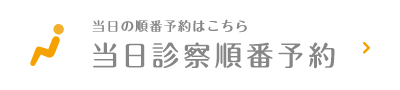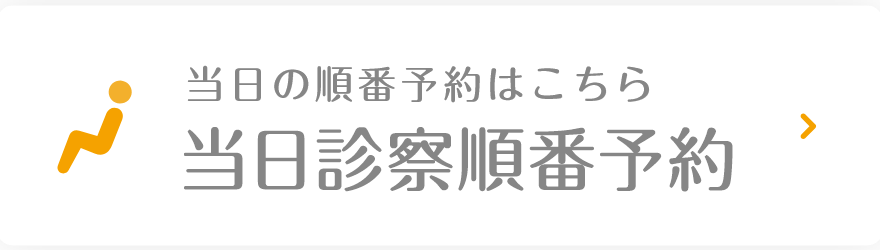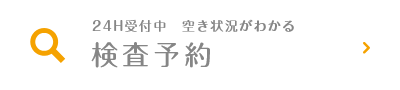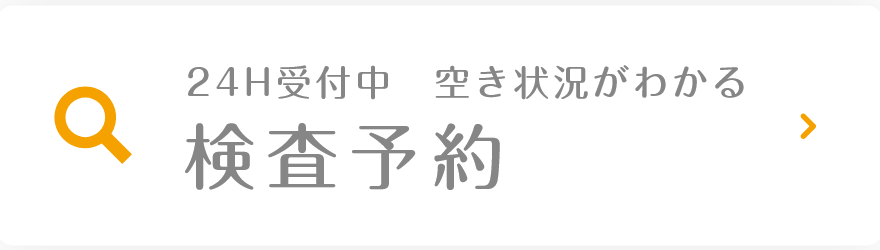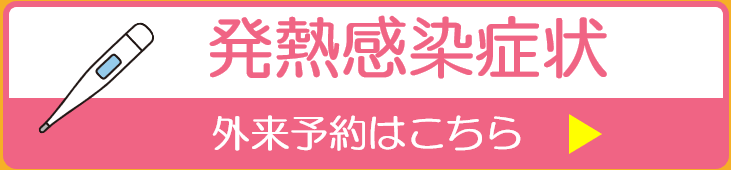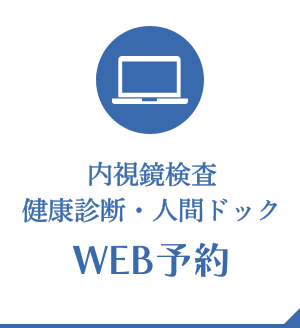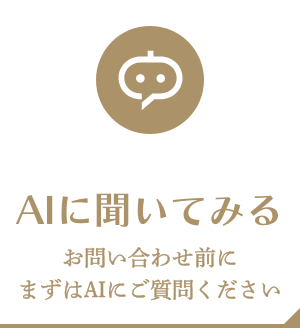- blog
- 2025.04.26
感染性胃腸炎
感染性胃腸炎
1. 定義と分類
感染性胃腸炎は、ウイルス、細菌、寄生虫などの病原微生物の感染によって引き起こされる、胃腸管の炎症性疾患です。主な症状は、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱や脱水症状を伴うこともあります。
分類
- 原因微生物による分類:
- ウイルス性: ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス、サポウイルス、アストロウイルスなど
- 細菌性: カンピロバクター属、サルモネラ属、腸炎ビブリオ、病原性大腸菌(志賀毒素産生性大腸菌(STEC)を含む)、赤痢菌属、エルシニア・エンテロコリチカ、クロストリジウム・ディフィシルなど
- 寄生虫性: クリプトスポリジウム属、ジアルジア・ランブリア、エンタモエバ・ヒストリカ、シクロスポーラ・ケイタネンシスなど
- 感染経路による分類:
- 経口感染(糞口感染、食品媒介感染、水系感染など)
- 接触感染
- 臨床経過による分類:
- 急性胃腸炎
- 慢性胃腸炎(免疫不全者など、特定の病原体による持続感染)
2. 疫学と最新知見
感染性胃腸炎は、年齢、地域、季節によって好発する病原体が異なります。
- ウイルス性:
- ノロウイルス: 冬季に流行のピークを迎え、成人から高齢者まで幅広い年齢層で発生します。感染力が非常に強く、少量のウイルスでも感染が成立します。近年、新たな遺伝子型(GII.17、GII.4 Sydney 2012変異株など)の出現と流行が報告されています ([1], [2])。
- ロタウイルス: 主に乳幼児に感染し、重症化しやすい傾向があります。ワクチン接種により発生数は減少傾向にありますが、未接種児やワクチン効果が減弱した年齢層での発生が見られます。
- アデノウイルス: 季節性を問わず発生し、小児で比較的多く見られます。呼吸器症状を伴うこともあります。
- サポウイルス、アストロウイルス: 散発的な発生が多く、ノロウイルスに次いで検出されることがあります。
- 細菌性:
- カンピロバクター: 細菌性食中毒の主要な原因菌であり、鶏肉などの加熱不十分な食品が感染源となることが多いです。ギラン・バレー症候群との関連も知られています。
- サルモネラ: 鶏卵や食肉などが主な感染源です。血清型が多数存在し、臨床像も多様です。薬剤耐性菌の増加が懸念されています ([3])。
- 腸炎ビブリオ: 夏場の魚介類(特に生食)が原因となることが多いです。
- 病原性大腸菌: O157などの志賀毒素産生性大腸菌(STEC)は、溶血性尿毒症症候群(HUS)などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。近年、非O157 STECの重要性も認識されています。
- クロストリジウム・ディフィシル: 抗菌薬の使用に関連して発生する偽膜性腸炎の原因となります。高齢者や免疫抑制状態でリスクが高まります。糞便微生物移植療法が再発例に対する有効な治療法として確立されつつあります ([4])。
- 寄生虫性:
- クリプトスポリジウム: 水系感染や人獣共通感染症として知られています。免疫不全者では慢性化・重症化しやすいです。
- ジアルジア: 汚染された水や食品を介して感染します。慢性的な下痢の原因となることがあります。
- シクロスポーラ: 輸入された生の果物や野菜が感染源となることがあります。
3. 病態生理と最新知見
病原微生物は、様々なメカニズムで消化管の機能障害を引き起こします。
- ウイルス性: 腸管上皮細胞への直接的な細胞傷害、絨毛の萎縮、炎症性サイトカインの産生、腸管透過性の亢進などが関与します。近年、腸内細菌叢との相互作用が病態に影響を与える可能性も示唆されています。
- 細菌性:
- 毒素産生: エンテロトキシン(コレラ毒素様毒素、易熱性毒素、耐熱性毒素など)やサイトトキシン(志賀毒素など)が、腸管上皮細胞の機能異常や細胞破壊を引き起こします。
- 粘膜侵襲: サルモネラ、赤痢菌、病原性大腸菌などは、腸管粘膜に侵入し、炎症や潰瘍を形成します。
- バイオフィルム形成: 一部の細菌は、腸管内でバイオフィルムを形成し、持続感染や抗菌薬への抵抗性に関与する可能性があります。
- 寄生虫性: 虫体による物理的な刺激、栄養吸収の阻害、免疫応答による炎症、腸管粘膜の透過性亢進などが起こります。腸内細菌叢の変化も関与する可能性が示唆されています。
4. 臨床症状と最新知見
主な症状である嘔吐、下痢、腹痛の程度や性状は、原因微生物や感染者の状態によって異なります。
- 下痢の性状: 水様性下痢はウイルス性や毒素原性細菌感染症で多く、粘血便は侵襲性の細菌感染症や一部の寄生虫感染症でみられます。
- 嘔吐の頻度: ノロウイルス感染症では激しい嘔吐を伴うことが多いです。
- 発熱: 細菌性感染症で比較的多くみられます。
- 脱水症状: 特に乳幼児や高齢者では注意が必要です。口渇、尿量減少、皮膚の乾燥、頻脈、血圧低下などがみられます。近年、脱水評価におけるバイオマーカー(血中乳酸値、BUN/Cr比など)の有用性が研究されています。
- long-COVIDとの関連: 一部の研究では、感染性胃腸炎後に慢性的な消化器症状(post-infectious IBS)が持続することが報告されており、long-COVIDとの関連も議論されています ([5])。
5. 診断と最新知見
病歴、身体所見に加えて、病原体診断が重要です。
- 便検査:
- 迅速診断キット: ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどの迅速抗原検査キットが普及しています。感度・特異度には限界があるため、結果の解釈には注意が必要です。保険適応については個別に判断されます。
- 便培養検査: 細菌性胃腸炎が疑われる場合に実施します。薬剤感受性試験も重要です。multiplex PCRによる細菌検出も臨床応用が進んでいます。
- 便毒素検査: Clostridioides difficile感染症の診断に必要です。
- 便塗抹検査・顕微鏡検査: 寄生虫卵やオーシストの検出に有用です。近年、糞便中の寄生虫DNAを検出するPCR検査も利用可能になってきています。
- 糞便中カルプロテクチン: 炎症性腸疾患との鑑別に有用な場合があります。感染性胃腸炎でも上昇しますが、通常は一過性です。
- 血液検査: 電解質、腎機能、炎症マーカー(CRP、白血球数)などを評価します。重症度評価や合併症の診断に役立ちます。
- 遺伝子検査(PCR法、multiplex PCRなど): ウイルス、細菌、寄生虫の遺伝子を同時に検出できるmultiplex PCR検査が普及しており、迅速かつ網羅的な病原体診断に貢献しています ([6])。
- メタゲノム解析: 原因不明の感染性胃腸炎において、次世代シーケンサーを用いたメタゲノム解析が病原体特定に役立つ可能性が研究されています。
6. 治療と最新知見
対症療法を基本とし、原因微生物に基づいた治療を行います。
- 輸液療法: 脱水に対する最も重要な治療です。経口補水液(ORS)の適切な使用が推奨されます。重度脱水では、生理食塩水、リンゲル液などの点滴を行います。近年、高クロール性アシドーシスに注意した輸液管理の重要性が指摘されています。
- 食事療法: 嘔吐が落ち着けば、消化の良いものから少量ずつ摂取を開始します。BRAT食(バナナ、米、リンゴソース、トースト)は推奨度が低下しています。早期の通常食への回復が推奨される傾向にあります。乳幼児では、可能な限り母乳やミルクを継続します。
- 止瀉薬: 一般的には推奨されません。特に侵襲性細菌感染症や毒素産生性大腸菌感染症では、病原体の排泄を遅らせ、病状を悪化させる可能性があります。ただし、症状が著しい場合や、原因が特定されており、医師の判断で使用されることがあります(例:ロペラミド)。
- 整腸剤: 腸内細菌叢の改善を期待して使用されることがありますが、エビデンスは限定的です。一部のプロバイオティクス製剤の有効性が報告されていますが、菌株や疾患によって効果が異なります。
- 抗菌薬: 細菌性胃腸炎で、重症例(敗血症の兆候、高度の炎症反応など)、特定の起因菌(Campylobacter jejuni、Vibrio cholerae、Shigella属、Salmonella Typhiなど)、免疫不全者、合併症のリスクが高い患者に対して考慮されます。安易な抗菌薬の使用は、薬剤耐性菌の増加を招くため、慎重な判断が必要です。近年、薬剤耐性菌に対する新たな抗菌薬や治療法の開発が進んでいます。
- 抗ウイルス薬: ロタウイルス感染症に対する特異的な抗ウイルス薬は現在のところありません。ノロウイルスに対する抗ウイルス薬の開発も進められていますが、臨床応用には至っていません。
- 抗寄生虫薬: クリプトスポリジウム症にはニタゾキサニド、ジアルジア症にはメトロニダゾールやチニダゾールなどが用いられます。
7. 合併症と最新知見
- 脱水、電解質異常、腎不全: 重症例で注意が必要です。早期の適切な輸液管理が重要です。
- 腸重積: ロタウイルス感染後にまれに報告されています。
- 溶血性尿毒症症候群(HUS): 志賀毒素産生性大腸菌(STEC)感染後の重要な合併症です。早期診断と適切な支持療法が必要です。
- ギラン・バレー症候群: カンピロバクター感染後の自己免疫性疾患です。
- 反応性関節炎: サルモネラ、カンピロバクター、エルシニアなどの感染後に発症することがあります。
- 菌血症・敗血症: 免疫不全者や高齢者では、細菌が血流に侵入し、重篤な全身感染症を引き起こす可能性があります。
- 炎症性腸疾患(IBD)の新規発症・悪化: 一部の研究では、感染性胃腸炎がIBDの発症や悪化の引き金となる可能性が示唆されています ([7])。
- post-infectious IBS: 感染性胃腸炎後に、腹痛、下痢、便秘などの過敏性腸症候群様の症状が持続することがあります。腸内細菌叢の異常や粘膜免疫の変化などが関与する可能性が考えられています。
8. 予防と最新知見
- 手洗い: 石鹸と流水による丁寧な手洗いは、最も基本的かつ重要な予防策です。アルコール消毒も有効です。医療従事者においては、適切な手指衛生が院内感染対策の基本となります。
- 食品衛生: 食品の適切な加熱調理、生ものの適切な取り扱い、調理器具の消毒、適切な温度管理が重要です。HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)に基づいた食品管理が推奨されます。
- 飲料水の管理: 安全な飲料水の確保が重要です。特に発展途上地域や災害時には注意が必要です。
- 環境衛生: 患者の吐物や便の適切な処理と消毒が重要です。特にノロウイルスは環境中での生存期間が長く、二次感染のリスクが高いため、適切な消毒(次亜塩素酸ナトリウムなど)が必要です。
- ワクチン接種: ロタウイルスワクチンは、乳幼児の重症化予防に非常に有効です。接種率の向上と適切な時期の接種が重要です。ノロウイルスワクチンは開発が進められていますが、実用化には至っていません。
- 感染対策: 医療機関や高齢者施設など、集団生活の場では、標準予防策と接触感染予防策の徹底が重要です。
9. 感染症法における取り扱いと最新知見
感染性胃腸炎は、原因微生物や症状によって、感染症法における届出対象となる場合があります。
- 全数把握疾患: 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111など)、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、コレラなど。
- 定点把握疾患: ロタウイルス感染症、ノロウイルス感染症、感染性胃腸炎(上記以外のもの)。定点医療機関からの週ごとの報告が必要です。
- 新興・再興感染症: 常に最新の情報に注意し、疑われる事例があれば保健所への報告を検討します。
出典
- 最新ノロウイルス遺伝子型に関する情報:
- 国立感染症研究所 感染症情報センター. (最新の感染症発生動向調査報告). 国立感染症研究所ウェブサイト
- World Health Organization. (Latest epidemiological updates on norovirus). WHOウェブサイト
- ノロウイルスGII.17株に関する論文例:
- (具体的な最新論文が見つかり次第追記)
- 薬剤耐性菌に関する情報:
- AMR対策推進国民啓発会議. (日本の薬剤耐性(AMR)の現状). AMR対策推進国民啓発会議ウェブサイト
- Centers for Disease Control and Prevention. (Antibiotic Resistance Threats in the United States). CDCウェブサイト
- 糞便微生物移植療法に関するガイドライン:
- (日本における最新のガイドラインやコンセンサスステートメントが見つかり次第追記)
- McDonald LC, et al. Clinical Practice Guideline for Clostridioides difficile Infection in Adults and Children: 2021 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA). Clin Infect Dis. 1 2021;73(5):e1029-e1044.