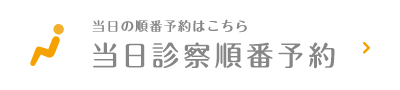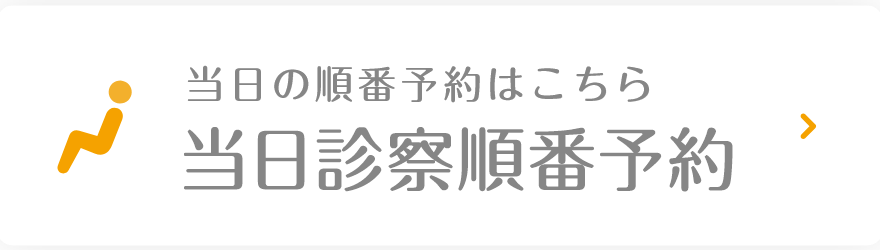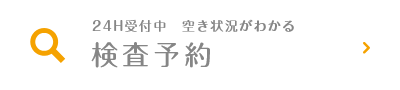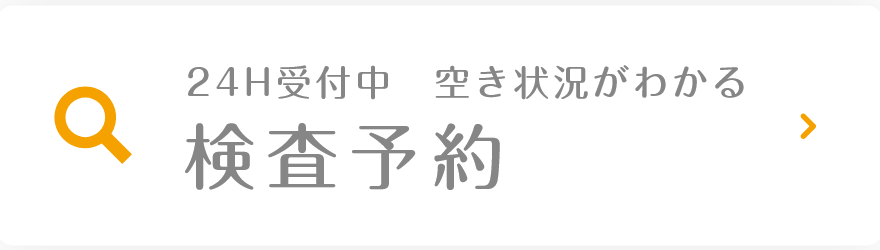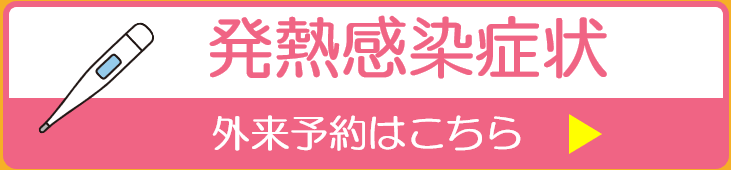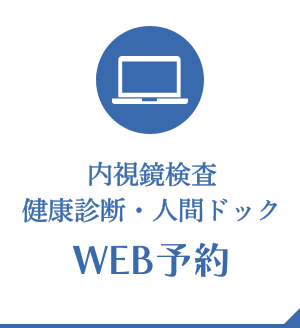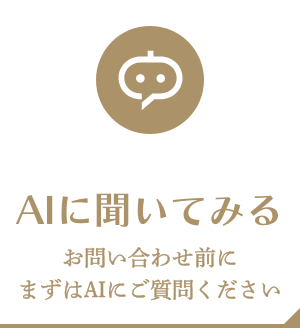アニサキス症|東戸塚メディカルクリニック(横浜市戸塚区)
生魚を食べた後の強い腹痛、それは「アニサキス症」かもしれません
アニサキス症とは、寄生虫の一種であるアニサキス幼虫が、生あるいは加熱不十分な魚介類とともに体内に取り込まれることで発症する感染症です。サバ、イワシ、カツオ、サンマ、アジ、サケなどの魚に寄生していることが多く、刺身や寿司などの生食を通じて体内に侵入します。日本では特に冬場に多く報告されています。
体内に侵入したアニサキスは、胃や腸の壁に刺入し、強い腹痛や吐き気を引き起こします。発症の背景にはアレルギー反応が関与しているとされ、稀にアナフィラキシーショックを起こすこともあります。感染しても症状が出ない方もいますが、激しい腹痛を伴う場合は早期の診断と対応が重要です。
症状と発症のタイミングについて
アニサキスが胃に侵入した場合、食後3〜4時間以内に、みぞおち付近を中心とした鋭い腹痛が突然出現します。波打つような痛みで、あまりの激痛に身動きが取れなくなるケースもあります。嘔気や嘔吐を伴うこともあり、「空吐き」のような症状が現れることもあります。
一方、アニサキスが腸に達した場合は、発症までに十数時間から数日を要することが多く、腹部膨満感や持続的な鈍痛、下痢、下血といった症状を呈することがあります。腸管の穿孔に至る重症例もあるため、注意が必要です。いずれも、生魚を食べた後に症状が現れた場合は、医療機関への早期受診が勧められます。
胃アニサキス症と腸アニサキス症の違い
胃アニサキス症は、急激に始まる激しい腹痛が特徴で、比較的診断がつきやすい傾向にあります。内視鏡で虫体を直接確認し、その場で摘出することで症状が劇的に改善するケースが多く見られます。
これに対して腸アニサキス症では、症状が比較的緩やかに進行し、胃のように直接観察できないため診断が難しいことがあります。発症頻度は低いものの、診断の遅れが重症化を招く可能性もあるため、腸管症状が長引く場合には注意が必要です。
検査方法について
胃アニサキス症が疑われる場合には、上部内視鏡検査(いわゆる胃カメラ)を行い、胃粘膜に刺入しているアニサキスを直接観察し、その場で摘出します。当院では鎮静剤を使用し、できる限り苦痛の少ない検査を提供しています。
腸アニサキス症が疑われる場合には、腹部CT検査や腹部超音波検査、小腸内視鏡などを用いて評価します。特に超音波検査では、腸管の壁が厚くなっている様子や腸液の貯留といった所見が参考になります。また、生魚の摂取歴などの問診や、アニサキスに対する特異的IgE抗体の有無を確認する血液検査も診断の一助となります。ただし、感染初期には陰性となることもあるため、総合的な判断が重要です。
治療方法と経過
胃アニサキス症の場合、内視鏡で虫体を摘出すれば、多くの場合、症状は速やかに改善します。腸アニサキス症では、基本的には絶食や点滴による保存的治療が行われ、虫体が明確に認められ症状が強い場合は、小腸内視鏡による摘出が検討されます。
補助的に、腹痛や吐き気を和らげる薬物療法を行うこともあり、アレルギー症状が認められる場合には、抗ヒスタミン薬やステロイドの投与が行われることもあります。
アニサキスは体内に残存しても1週間程度で自然死滅するとされており、虫体の摘出が難しい場合でも、慎重に経過を見守る中で症状が軽快するケースもあります。
予防のために気をつけたいこと
アニサキス症は、食生活の工夫によって予防が可能な感染症です。生の魚介類を食べる際には、新鮮なものを選ぶだけでなく、内臓部分を避ける、目視でアニサキスの有無を確認するといった注意が重要です。アニサキスは一般的な調味料では死滅しないため、酢や醤油、わさびなどでの予防効果はありません。
確実な予防には、魚を70℃以上で十分に加熱する、または−20℃以下で24時間以上冷凍することが推奨されています。アレルギー体質の方の中には、加熱魚でも反応を起こす方もいらっしゃるため、注意が必要です。
内視鏡検査をご希望の方へ
当院では、アニサキス症が疑われる方に対し、消化器内視鏡専門医が対応いたします。検査は予約制ですが、急な腹痛などの場合には柔軟に対応できるよう調整しております。痛みの原因がはっきりせず不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。
経験豊富な医師による丁寧な内視鏡検査を通じて、症状の早期改善を目指します。